
電子署名を提供するサービスが増えましたが、不動産業や金融業といった特定の業種を除いて、電子署名を導入する法的な問題点はそれほどありません。ここで、契約について何に注意すべきなのか、予防法務という観点で見てみましょう。
特許法では、過去に偽の譲渡証書を用いて特許権を事実上盗み出すという事件がありました。契約書や譲渡証書は、紙であろうが電子であろうが、偽造しようと思えばいくらでも偽造できますし、防止することは不可能です。そして、電子署名サービスの売りはこの偽造防止の部分です。電子署名された契約書はその後の改ざんが技術上不可能となる上に、全てのアクセスログが記録されることから、紙の証書類よりも信ぴょう性が高くなるというメリットがあります。
一方、電子であろうが紙であろうが、これらの偽造・改ざん行為は契約行為を超えてもはや犯罪の域に足を踏み入れています。これはもはや別事件であり、契約の締結においては、偽造の防止うんぬんよりも誰と何を契約するかといった、その内容の方がはるかに重要です。
まず、契約書の住所と氏名です。この欄は半ば「ここが訴状の送付先です」という意味です。訴訟は、相手方に郵便局が訴状を送達できないと開始できません。そして、仮に訴状が届いても、その名宛てした個人が正しく契約ができる人であったことも必要です。会社と契約したのであれば、少なくとも個人名が役員でなければならず、その契約をする権限があったことにも確証がある必要があります。最後に、必要な約束を正しい用語・正しい文章でしていたことが必要です。法律家からしてみれば、契約書が紙か電子かなどは瑣末な問題にすぎず、とにかく正しい相手と正しい約束を正しい用語と文章で記録に残したか、問題点の99.9%はこちらなのです。
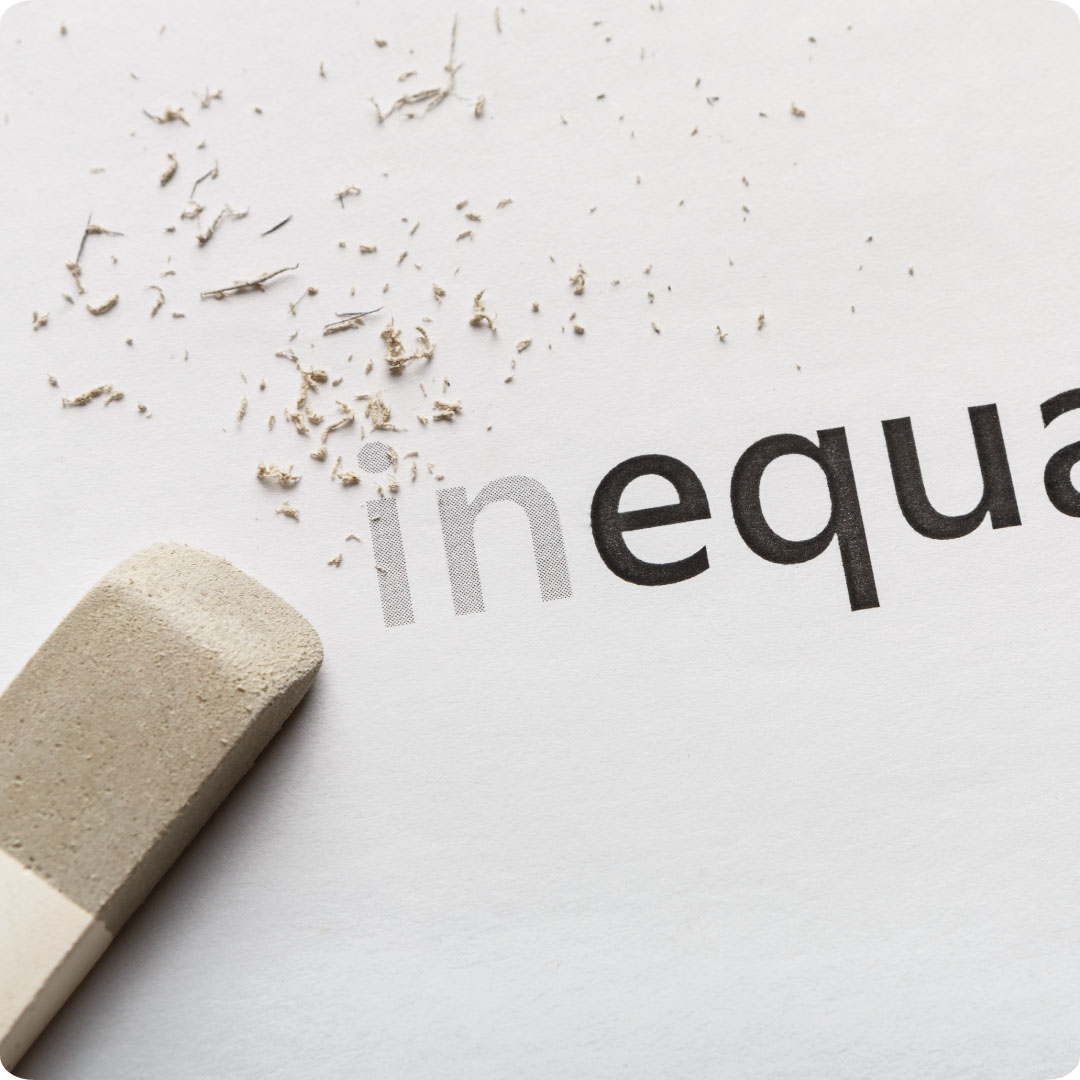
契約に関する対策の疑問・ご質問は、お問い合わせフォームからフィラー特許事務所宛にファーストコンタクトをお送りください。ただし、紛争の解決に関する相談には対応できません。あくまで対策(ビジネスモデルの構築)についてのアドバイスが特許事務所の仕事です。ファーストコンタクトのご利用は無料です。