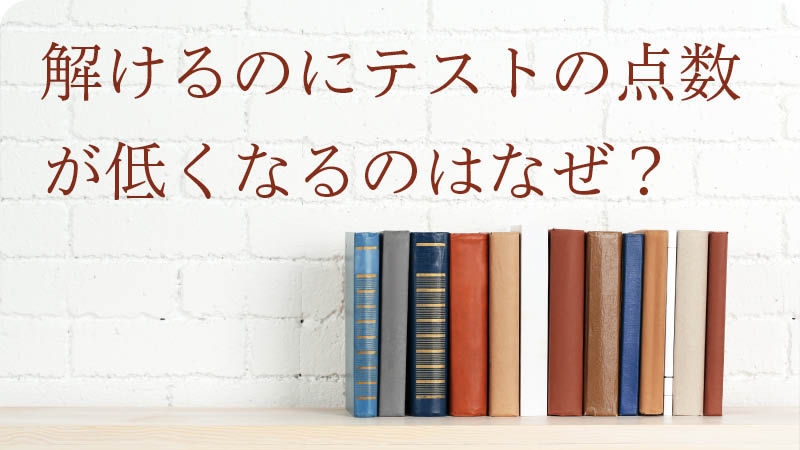
B君は、必死に練習をして筆算の足し算ができるようになりました。しかし、学校のテストではなかなか点数が上がらず、点数を見て叱られることも多くなっていました。B君は、やり直しではきちんと計算ができているのに、最初の簡単な数問しか解答しておらず、ほとんどが空白のままテストをやり終えていました。
事例の真相
B君はもともと計算が苦手ではなく、筆算の仕組みも理屈も十分に理解していました。しかし、テストの答案用紙を見ると、明らかにすぐに解けるような最初の数問を解いただけで、その後の問題を放棄しているような特徴が見られました。
調べてみると、B君はテスト開始の合図があっても鉛筆を転がしたり、周囲をキョロキョロしながらなかなか解答に取り掛かることがなく、テストの終了間際の5分くらいになって、ようやく問題に取り掛かるというパターンを繰り返していたようなのです。
B君は、問題用紙にずらりと並んだ計算式に視覚的に圧倒され、それが原因でなかなかテストに取り掛かることができませんでした。そして、テスト時間の終了とともに「先生がプリントを持って行った」といって、もうやらなくていいんだと安心していたのです。
制限時間と納期の概念
前回のSHIEN TIPSで、「時間を区切る練習をしてください」という記事を挙げましたが、「終わるまで止めさせない」という方法が習慣化してしまうと、時間内に解くという概念の形成が遅れるおそれが生じてしまいます。
いくら計算ができても、テスト本番で解答できないのであれば、社会的には計算ができないという評価になります。また、10分で5問出されているから、1問あたり2分で解かないといけないという、工数と与えられた時間からスケジュールを立てるという練習も必要になってきます。
時間割によって半ば強制的にスケジュールを切るというやり方は、このような計画能力を養うための練習から来ています。